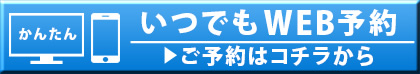遺言書 検認 申立
- 自筆証書遺言の検認|流れや弁護士に依頼するメリットなど
これらのうち、「公正証書遺言」の場合には、検認手続を採る必要はありませんが、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合には、検認手続を採る必要があります。 検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や署名などの内容を明確にする手続きです。検認を行わなければ、遺言書の偽造や捏造が行...
- 遺言書の検認とは?必要性や申立ての流れを弁護士が解説
自宅で見つかった自筆証書遺言などの遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で「検認」の手続を行う必要があります。今回は遺言書の検認の必要性や申立ての流れなどを解説していきたいと思います。遺言書の検認を行う必要性自筆証書遺言などを家庭裁判所で「検認」する目的として、遺言書の偽造や変造を防ぐとともに、遺言内容の存在と形式を...
- 遺言書の種類と効力
■遺言書の種類遺言書は、一般に以下のような種類に分けることができます。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で紙とペンなどを用いて作成するものをいいます。いつでも自分だけで作成できるため負担は小さいといえますが、形式等に誤りが生じやすいため注意が必要です。 ・公正証書遺言公正証書遺言とは、遺言者が2人...
- 相続の流れ
■遺言書の確認遺言があるかどうかでその後の手続きが異なるため、遺言書の有無を確認します。遺言書があった場合、原則としてその遺言に従って相続財産が分けられることになります。遺言書がなかった場合、後述する遺産分割協議を行うことになります。■相続人および相続財産の調査遺産分割協議に向け、相続人が誰であるか、また相続財産...
- 成年後見制度とは
後見開始申立書や、親族関係図、診断書(判断能力が欠けていることの証明)等の必要書類を準備して、判断能力が低下している人、すなわち被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行いましょう。 後見人が選任されると、当該後見人が被後見人を代理して、遺産分割協議に参加できます。
- 婚姻費用分担請求
「婚姻費用分担請求」とは、婚姻費用に関する決定を行うため、家庭裁判所に対し、調停または審判の申立てをすることを指します。調停手続では、家庭裁判所が、当事者双方から財産や収入などの事情を聞き、解決案を提示、または必要な助言を行うことによって、最終的に合意を目指すことになります。 それでもなお結論がまとまらず、調停が...
- 相続法改正で変わった点とは
今回の相続法改正によって、法務局における遺言書の保管等に関する法律が設けられました。この法律は、自筆証書遺言(民法968条)を法務局が保管してくれるサービスについて定めた法律です。遺言者は、遺言書が紛失や偽造、隠匿されるおそれなく遺言書を保管させることができます。 ④特別の寄与改正前では、生前の看護などによる寄与...
- 債務整理(個人再生、自己破産)手続きで必要になる財産目録とは
個人再生や自己破産の債務整理を行う場合、開始手続の申立書にいくつかの書類を添付して、裁判所に申立てを行う必要があります。その書類のうち、「財産目録」についてご説明します。 個人再生とは、裁判所に申し立てをして、借金の元本を大幅に減額してもらう債務整理方法です。個人再生で提出する財産目録は、債務者が借金を支払いきれ...
- 生前贈与のメリットと手続き方法
遺言書に不備があれば故人の希望を反映させることができない場合があるところ、生前贈与を行えば、贈与者が相手を自由に選択でき、何を贈与するかも自由に決めることができます。したがって、特定の財産を指名した相手に確実に承継したい場合に、大きなメリットがあるといえます。 また、以下の制度を利用すれば、相続税の対象となる財産...
- 厚木市の債務整理は弁護士にご相談ください
自己破産は、裁判所に申立てを行い、一定の所有財産を処分することによって借入返済額を帳消しにする方法です。借金額にも制限がないため、収入の少ない方が利用しやすい債務整理方法となっています。特に、無収入の方が利用できる債務整理方法は自己破産のみです。自己破産の特徴は所有財産の処分ですが、全ての財産を失うわけではありま...
- 相続財産の調査方法
相続が発生すると、有効な遺言書がある場合を除き「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議を円滑に行うため、また協議後のトラブルを防止するためにも、協議に際して、相続人が誰であるのか、および相続財産は何か、といった事項を明確にしておく必要があります。 まず、相続の開始を知った日から3か月を経過すると、相続人は相続財産...
- 面会交流を拒否したい方へ|拒否できる正当な理由やリスクについて
正当な理由なく、面会交流を拒否し続けると親権者変更の申立が行われる可能性があります。そして、最悪の場合、親権者を変更すべきであると認められれば、親権者が変更され、子どもと一緒に生活できなくなってしまいます。 井上雅彦法律事務所では、相模原市、町田市、横浜、厚木を中心に神奈川、東京、埼玉、静岡で幅広く活動しておりま...
- 離婚調停の流れ|調停委員からはどんなことを聞かれる?
①離婚調停の申立まずは家庭裁判所へ離婚調停の申立を行います。原則的には、相手方の住所地を管轄している家庭裁判所に申し立てる方法によって行います。 ②第一回調停期日の決定離婚調停の申立を受理し、家庭裁判所が第一回調停期日の決定次第、当事者双方に通知を行います。 ③第一回調停期日期日通知書に記載された日時と場所で第一...
- 相続手続の流れを分かりやすく解説!
遺産相続の手続に関しては、遺言書の有無や遺産の多寡によっていろいろなケースが考えられます。もちろん個々のケースに確実に対応するためには、法律の専門家に協力を仰ぐのがベストでしょう。ここでは、一般的に考えられる相続の流れに沿って、どのような手続が必要になるのかを解説していきたいと思います。遺言書の有無と有効性を確認...
- 離婚の種類はいくつある?
調停の申立て第1回調停期日話し合いの継続(複数回)合意形成調停調書の作成離婚届の提出調停離婚のメリット・デメリット調停離婚のメリットは、中立的な立場の第三者が介入するため、法律の知識のあるなしに関わらず公平な解決を期待できる点です。専門的な知識を持つ調停委員が仲裁し、必要に応じてアドバイスをもらえる点もメリットが...
- 公正証書遺言があってももめるのはどんなケース?対策も併せて解説
さらに、不備による無効や偽造、遺言書の内容に関する争いなどが起きにくいことが特徴です。しかし、公正証書遺言を残したからといってあとからもめる場合もあります。公正証書遺言があってももめる公正証書遺言があったとしても、もめるケースは次の通りです。 遺言能力が欠格事由にあたるケース遺留分侵害にあたるケース遺言能力が欠格...
- 弁護士に離婚・親権問題を依頼するメリット
調停や裁判では、申立書など書類の提出が必要になります。さまざまな書類はただ書けばよいというものではなく、法的な根拠に基づき、調停などが有利に進むよう記載する必要があります。弁護士に依頼することで、こうした法的な書類の作成や手続きを代行してもらえます。代理人として出廷してもらうことで、効果的な主張をしてもらうことも...
- 調停離婚の流れとは?手続きと進め方を解説
決定した内容を申立書に記載する相手方の管轄エリアにある家庭裁判所に提出する家庭裁判所で話し合いをする調停調書を作成し、離婚が成立する申し立ての趣旨と実情を決めるまず、調停で求める内容や離婚に至る理由を明確にします。たとえば、慰謝料、財産分与、親権者の決定、養育費の支払いなど、相手に求める条件を整理しましょう。また...
- 離婚協議書を公正証書で残して、離婚後のトラブルに備えよう
「強制執行認諾約款」を公正証書に記載すると、即座に強制執行の申立てができます。一方、「強制執行認諾約款」の文言がない公正証書の離婚協議書では、債務不履行に対して訴訟、強制執行の申立ての手順が必要となります。養育費や特別費用など毎月発生する費用が協議内容に含まれる場合に、「強制執行認諾約款」の記載は非常に効果的です...