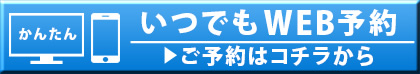遺言書の検認とは?必要性や申立ての流れを弁護士が解説
自宅で見つかった自筆証書遺言などの遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で「検認」の手続を行う必要があります。
今回は遺言書の検認の必要性や申立ての流れなどを解説していきたいと思います。
遺言書の検認を行う必要性
自筆証書遺言などを家庭裁判所で「検認」する目的として、遺言書の偽造や変造を防ぐとともに、遺言内容の存在と形式を公的に確認することが挙げられます。
一部の遺言書は、検認を経ないと効力が認められません。相続人全員に遺言書の存在を知らせ、後の紛争を防止するためにも重要です。
ただし、検認は遺言の有効性自体を判断するものではありません。
検認が必要ない遺言書
すべての遺言書の種類で検認の対象となるわけではありません。
公正証書遺言は、公証人のもとで作成されており、既にその存在と内容が公的に証明されているため、家庭裁判所での検認手続きは不要とされています。
また、自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用している場合には、検認の手続きが不要です。
遺言書の検認の申立ての流れ
家庭裁判所で遺言書の検認の申立ての流れは以下のとおりです。
検認の申立てに必要な書類を準備する
遺言書の検認を申立ては、遺言書を保管していたひとや発見した相続人が行います。
申立てに必要な書類は、以下のとおりです。
- 検認申立書
- 遺言書の原本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 申立人の住民票
上記の他にも状況によって必要になる書類もあります。
家庭裁判所への申立て
申立てに必要な書類をそろえたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
申立費用としては、800円分の収入印紙と切手が必要です。
検認期日の通知と出席
家庭裁判所は、検認の申し立てを受けると、相続人全員に検認期日の通知を送付します。
検認期日当日は遺言書を開封し、相続人は同席の上、内容や形式を確認し、検認完了したら、検認済証明書が発行されます。
この証明書によって、遺言の内容に基づいた相続登記や預貯金の解約などの手続きができるようになります。
まとめ
今回は遺言書の検認とはなにか、また簡単な手続きの流れについて解説していきました。
自宅などで見つかった遺言書は、検認がないとその効力を対外的に発揮することができません。
ただし、検認はあくまで遺言書が存在していることを示す手続きであり、内容が各相続人の権利を侵害していないなどを証明するものではありません。
遺言に関して相続トラブルになりそうな場合には、弁護士への相談を検討してみてください。