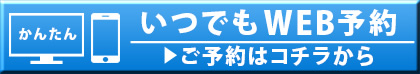遺留分の割合と遺留分額の具体的な計算方法を解説
相続に関する重要な権利として「遺留分」があります。
遺言で財産のすべてを誰かに譲ると決めても、法定相続人には最低限の相続分が保障されています。
この遺留分制度は、相続による財産分配において相続人の生活を守るための重要な仕組みです。
本記事では、遺留分の基本的な内容から具体的な計算方法まで、わかりやすく解説していきます。
遺留分についての基礎知識
遺留分は、法律によって特定の相続人に必ず残すことが定められた、相続財産の一部分を指します。
遺言で財産を誰かに譲る場合でも、相続人の生活を守るためにこの遺留分を確保しなくてはいけません。
相続における重要な権利保護の制度として、相続人の最低限の権利を保障する役割を果たしています。
遺留分を受け取ることができる相続人
民法1042条は、遺留分を受け取る権利を持つ相続人を明確に定めています。
配偶者、子、直系尊属(親や祖父母など)に遺留分の権利が認められますが、兄弟姉妹には遺留分の権利は認められていません。
相続人となる子が既に亡くなっている場合は、代襲相続人である孫にも遺留分の権利が引き継がれます。
一方で、兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続人となった場合、兄弟姉妹に遺留分の権利がないため、甥や姪にも遺留分の権利は発生しません。
遺留分の具体的な割合
遺留分の割合は、法定相続割合を基準に定められています。
相続人が直系尊属(親や祖父母)のみの場合は法定相続割合の1/3、それ以外の場合は1/2です。
具体的な遺留分の割合は以下のとおりです。
相続人の組み合わせ | 法定相続分 | 遺留分の割合 |
配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2 | 配偶者1/4、子1/4 |
配偶者と父母 | 配偶者2/3、父母1/3 | 配偶者1/3、父母1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 | 配偶者1/2、兄弟姉妹なし |
配偶者のみ | 配偶者全部 | 配偶者1/2 |
子のみ | 子全部 | 子1/2 |
父母のみ | 父母全部 | 父母1/3 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹全部 | 遺留分なし |
なお、直系尊属のみが相続人となるケースはまれであり、多くの場合は法定相続割合の1/2が遺留分となります。
遺留分額の具体的な計算方法
遺留分額は、遺留分算定の基礎となる財産額に遺留分の割合を掛け合わせることで、具体的な遺留分額を求めることが可能です。
計算の際には、以下の2つの計算式を使用します。
【遺留分算定の基礎となる財産額】
基礎となる財産額 = 相続開始時の財産 + 贈与財産・特別受益の価格 - 相続債務の全額
【遺留分の具体的な割合】
遺留分の割合 = 総体的遺留分 × 法定相続分の割合
それぞれの要素について詳しくみていきましょう。
被相続人の相続開始時の財産を把握する
遺留分を算定する際の基礎となるのは、被相続人が有する相続開始時点での財産です。
預貯金は通帳や残高証明書で正確な金額を確認できますが、不動産などは適切な評価方法で算出する必要があります。
不動産の評価方法は、地価公示・都道府県地価調査、相続税路線価、固定資産税課税評価額、不動産鑑定評価額、不動産業者の査定価格などです。
なお、財産評価の基準時は必ず相続開始時となります。
遺留分の計算に加える贈与財産・特別受益の範囲
遺留分の算定では、相続開始前の贈与財産も基礎となる財産に含めなくてはいけません。
相続開始前1年以内の贈与は、受取人が相続人であるかどうかを問わず、遺留分の基礎財産に加算されます。
特別受益についても、以下のような場合は遺留分の基礎財産に含まれるので注意しましょう。
- 婚姻や養子縁組に際しての贈与
- 生計を立てるための資金としての贈与
- 多額の生命保険金の受け取り
遺留分の計算では、相続開始前10年以内の特別受益が基礎財産に加算されます。
また、贈与を受けたひとと、被相続人の双方が遺留分を侵害することを知っていた場合は、期間に関係なく基礎財産に加えることが定められています。
このように贈与財産や特別受益を計算に含めることで、相続人間の公平性が保たれているのです。
負債がある場合は差し引く
遺留分の計算では、被相続人が残した債務の全額を基礎財産から差し引く必要があります。相続において債務に含まれるのは、被相続人の借入金や未払いの医療費などです。
ただし、葬儀費用については注意が必要です。
葬儀費用は相続人が負担すべき費用であり、被相続人の債務には該当しないため、遺留分の計算から除外することが定められています。
遺留分の割合をかけて算出する
基礎財産の確定後、遺留分の割合を掛けることで最終的な遺留分額が決まります。
遺留分の基本的な割合は法定相続分の2分の1となりますが、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1です。
相続人の組み合わせによる遺留分の具体的な割合は以下のとおりです。
- 配偶者と子の場合:配偶者は4分の1、子は4分の1
- 配偶者と父母の場合:配偶者は3分の1、父母は6分の1
- 配偶者のみの場合:配偶者は2分の1
- 子のみの場合:子は2分の1
- 父母のみの場合:父母は3分の1
これらの割合を基礎財産に掛けることで、各相続人の具体的な遺留分額を算出することができます。
まとめ
遺留分は、相続人の生活を守るために法律で定められた重要な権利保護の制度です。
遺留分額は、相続開始時の財産に贈与財産を加え、債務を差し引いた金額に、法定の割合を掛けて計算します。
相続人の組み合わせによって遺留分の割合が異なり、財産の評価方法も複数存在するため、計算は複雑になることがあります。
遺留分に関する問題は相続人間の争いに発展しやすいため、正確な計算や権利行使については、専門知識を持つ弁護士に相談することがおすすめです。