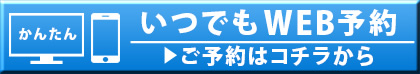調停離婚が成立しなかった時の裁判離婚の流れと期間
当事者間の話し合いによって離婚が成立しないとき、家庭裁判所の協力をもとに離婚成立を目指します。
まずは調停によって離婚を目指しますが、調停が成立しなかった場合には、裁判を行います。
この記事では、裁判離婚の流れと期間について解説します。
離婚の成立について
当事者間の話し合いで離婚に合意した場合、離婚届を提出することで離婚が成立します。
しかし離婚に合意しない場合や、養育費や慰謝料など離婚の条件がまとまらない場合には、離婚を成立させられません。
このようなときには、家庭裁判所を介して離婚を成立させます。
まずは調停委員を通して話し合いを行い、合意を目指します。
調停によって合意に至らなかった場合には、家庭裁判所へ訴訟を起こし、裁判を利用して離婚の成立を目指します。
裁判を行った場合、たとえ相手が離婚を望んでいなくても、離婚の判決が確定すると離婚成立となります。
ただし裁判を行うには、調停を経ていなければいけません。
裁判離婚について
裁判によって離婚するには、法律で定められた離婚事由がなければいけません。
具体的な法定離婚事由は次の通りです。
- 第三者との性行為
- 正当な理由なく同居・協力・扶助の義務を怠った
- 3年以上生死不明
- 重い精神疾患にかかり回復の見込みがない
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、DVやギャンブル、借金など夫婦生活を継続することが難しい事象です。
単なる性格の不一致では認められませんが、性格の不一致により長期間の別居状態となり、別居の解消が困難な場合には離婚事由として認められます。
裁判離婚の流れと期間
離婚の裁判は次の流れで行います。
- 訴状の提出
- 答弁書の提出
- 口頭弁論
- 本人尋問
- 判決
離婚の裁判は半年~2年ほどかかることが一般的です。
通常、1回の口頭弁論で判決が下されることはなく、裁判官が争点について判断できる状況になるまで、何度も口頭弁論などを行わなければいけません。
争点が多い場合や決定的な証拠がとぼしい場合には審理の回数が増え、長引く傾向があります。
訴状の提出
夫婦どちらかの住所地の家庭裁判所に訴状を提出し、訴訟を起こします。
必要な書類は、訴状と夫婦の戸籍謄本です。
そのほか、必要に応じて証拠となる書類の提出が必要です。
訴状には基本的な個人情報のほか、慰謝料や養育費、年金分割などについて請求内容を記載します。
また、該当する法定離婚事由についても具体的に記載します。
答弁書の提出
家庭裁判所へ提出した訴状は相手方にも送られます。
訴状を受け取った側は、その訴状に対する反論などを答弁書にまとめて裁判所へ提出します。
なお答弁書を提出せず、1回目の呼び出しにも応じなかった場合には、相手方が訴状の内容をすべて認めたものと判断されます。
口頭弁論
訴訟を起こしてから1~2か月ほどで1回目の口頭弁論期日となります。
訴状や答弁書の内容と、次回までに準備するものの確認を行います。
1回目の口頭弁論が終了すると、その後は必要に応じて月1回ほどのペースで弁論や弁論準備手続きが行われます。
弁論準備手続きでは、相手の主張に対する反論などを行い、争点を整理していきます。
このとき、話し合いによって双方が争点について合意できそうな場合には、裁判官から和解を勧められることもあります。
当事者双方が和解に合意すると和解離婚となり、裁判は終了します。
合意できない場合には裁判が継続します。
本人尋問
争点が整理され、和解の見込みもない場合には、尋問を行って事実関係や証拠の信ぴょう性を示す手続きが行われます。
当事者本人が、離婚相手やその弁護士、裁判官などからの質問に答えます。
たとえば双方の主張が食い違っている場合、裁判官はどちらの主張が正しいのか、提出された証拠をもとに判断しなければいけません。
証拠調べをしていくなかで本人に尋問を行い、事実関係を認定していきます。
判決
裁判官が判決を下すと離婚の裁判は終了です。
判決の内容に不服がある場合には、判決受取後14日以内に高等裁判所へ控訴することも可能です。
控訴せずに離婚の判決が確定した場合、その時点で離婚が成立します。
その後、判決確定から10日以内に市区町村役場へ離婚届を提出しなければいけません。
提出の際には判決謄本と判決確定証明書を合わせて提出します。
まとめ
この記事では裁判離婚について詳しく解説しました。
離婚の裁判を起こすには、まず調停を経ていなければいけません。
裁判では月1回ほどのペースで口頭弁論などを行います。
判決を下せる状況になるまで繰り返し行われるため、争点が多い場合などは裁判が長引く恐れもあります。
通常であれば1~2年ほどで終了することが一般的ですが、スムーズに裁判を進めるには決定的な証拠の提出が不可欠です。
裁判離婚をお考えの方は、弁護士までご相談ください。